公表されました!
外部リンク(ASBJ):「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」
平成27年5月26日にリリースされた公開草案から、一部修正を行った上で、平成27年12月28日に公表されました。
最終出社日の方も多かったことが予想されるギリギリのタイミングでの公表ですね。。
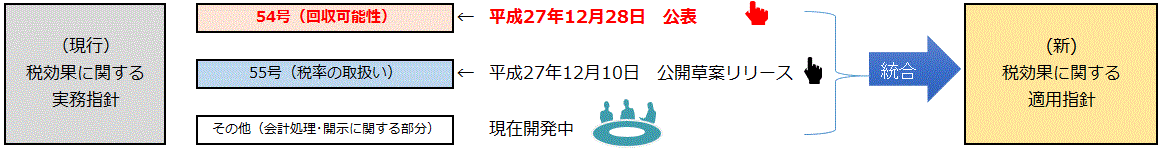
繰延税金資産の回収可能性とは?
繰延税金資産の回収可能性とは、繰延税金資産が将来支払う予定の税金を減額する効果があるかどうか、をいいます。
繰延税金資産は、将来減算一時差異に法定実効税率を乗じて算定しますが、この将来減算一時差異には、読んで字のごとく、『将来』の課税所得を『減算』する効果があります。
但し、将来の課税所得を減算するためには、将来の課税所得が発生していなければその効果はありません。
たとえば、将来減算一時差異が100あった場合、将来の課税所得が150とすれば、150-100=50となり、将来の課税所得を150⇒50へと減算する効果がありますが、一方で将来の課税所得が80だとすると、80-100=△20となり、通常納税額はマイナスとはならないことから、80までしか将来の課税所得を減算する効果がありません。
このように、繰延税金資産の回収可能性は、将来の税金を減額する効果分だけ認められるものになることから、将来の課税所得が見込めない分は、税金を減額する効果というものが無く、繰延税金資産の回収可能性は無い、ということになります。
従前までは、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(以下66号)において定められていましたが、実務上議論になっている諸問題があったことで、見直しの審議が重ねられ、今般適用指針が公表されることになりました。
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の概要
用語の明確化
たとえば従来は、至るところに「課税所得」と使われていましたが、意味合いが異なるものが混在していました。勿論、個別税効果実務指針21項に「将来の課税所得の見積りに関して、本項で述べる課税所得とは・・・」とあるので、意味合いが異なる旨の記載自体は以前からあったのですが、そこまで知らない一般読者には不親切だなぁと感じていました。
改正により各用語の定義が明確化されるとともに、従来から使われている用語についても改めて新設して定義されています。
過去に関する要件については「課税所得」、将来に関する要件については「一時差異等加減算前課税所得」というように、しっかりと分けて使用されているので、より明瞭になっています。
会社分類に応じた繰延税金資産の回収可能性の取扱い
従前の66号の枠組みを基本踏襲した上で、取扱いの一部について見直されました。
具体的には、企業を5つに分類した上で、分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積もる、といった枠組みは従来と同様ですが、その各分類ごとに取扱いの一部が見直され、会計上の指針としての取扱いを明確化するために、分類ごとの『要件』を設定し、要件に基づいて企業を分類するように改正されました。
分類ごとの要件は下記の通りです。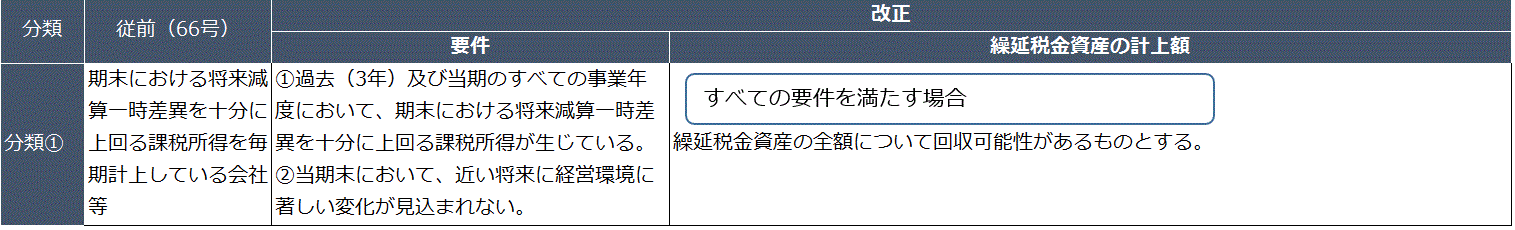
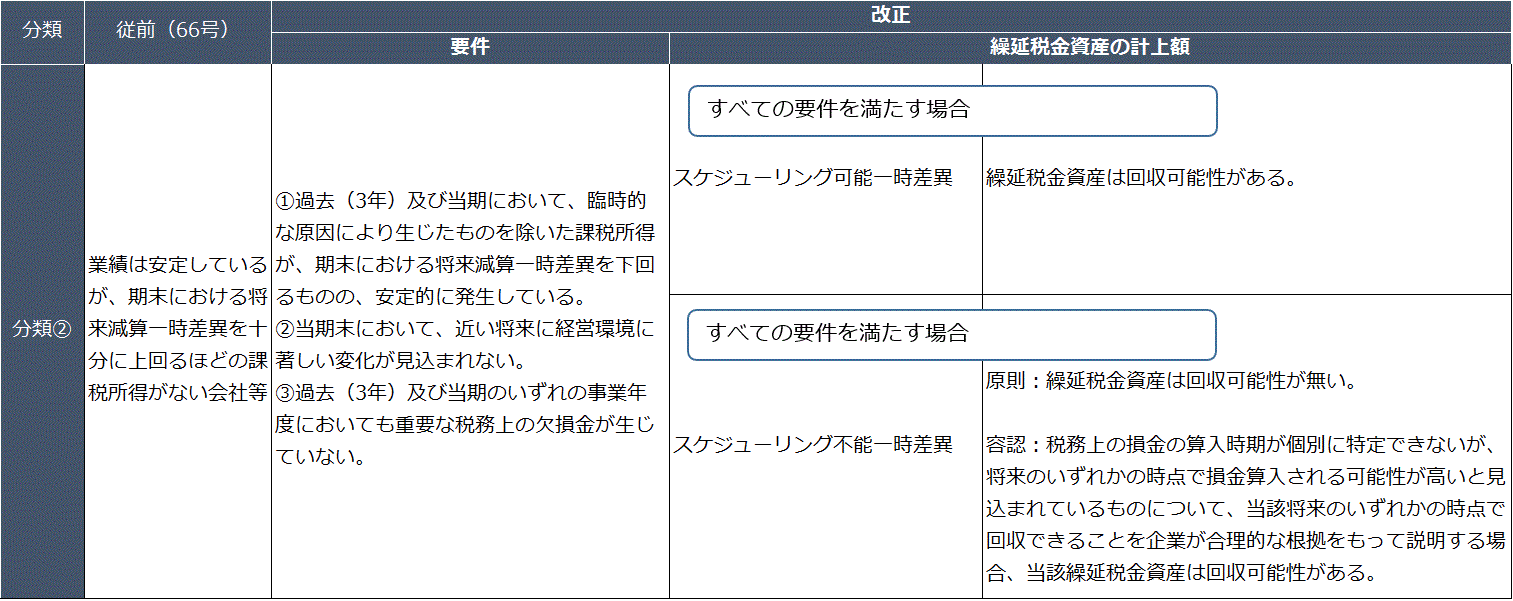
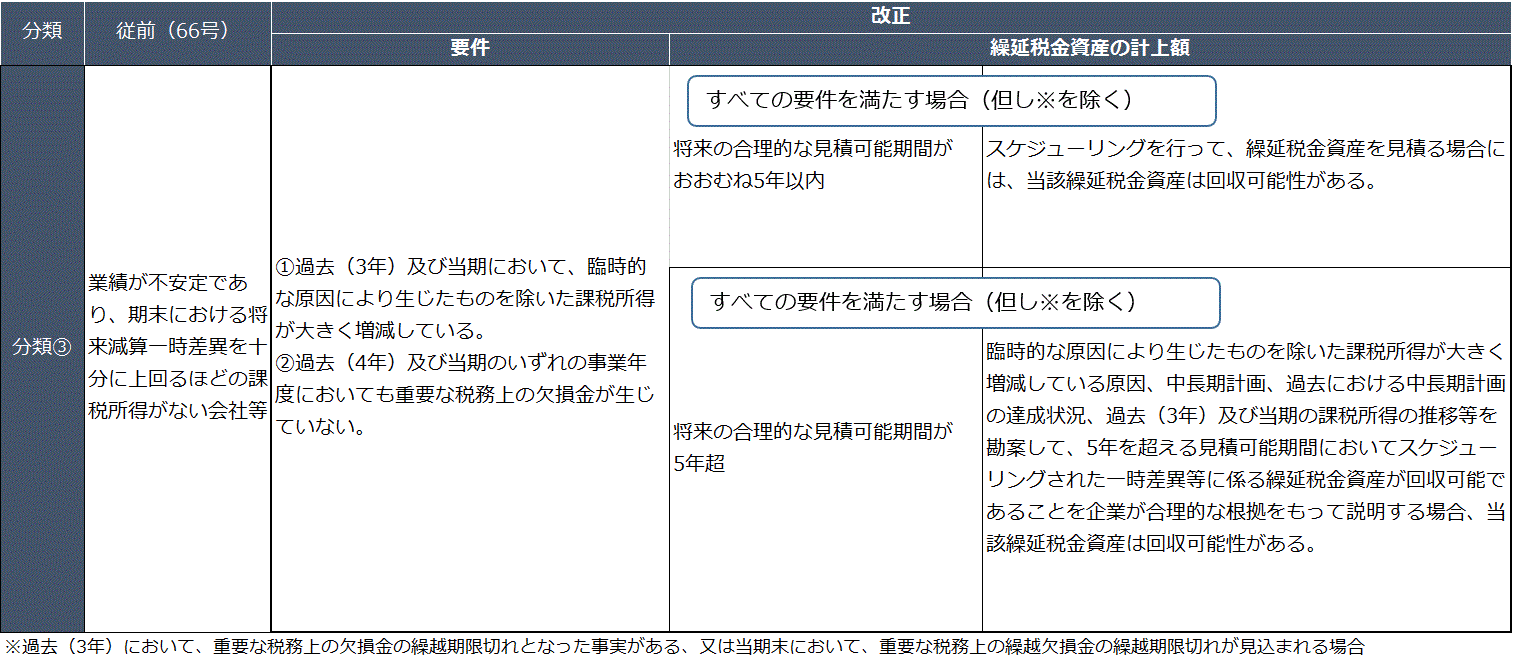
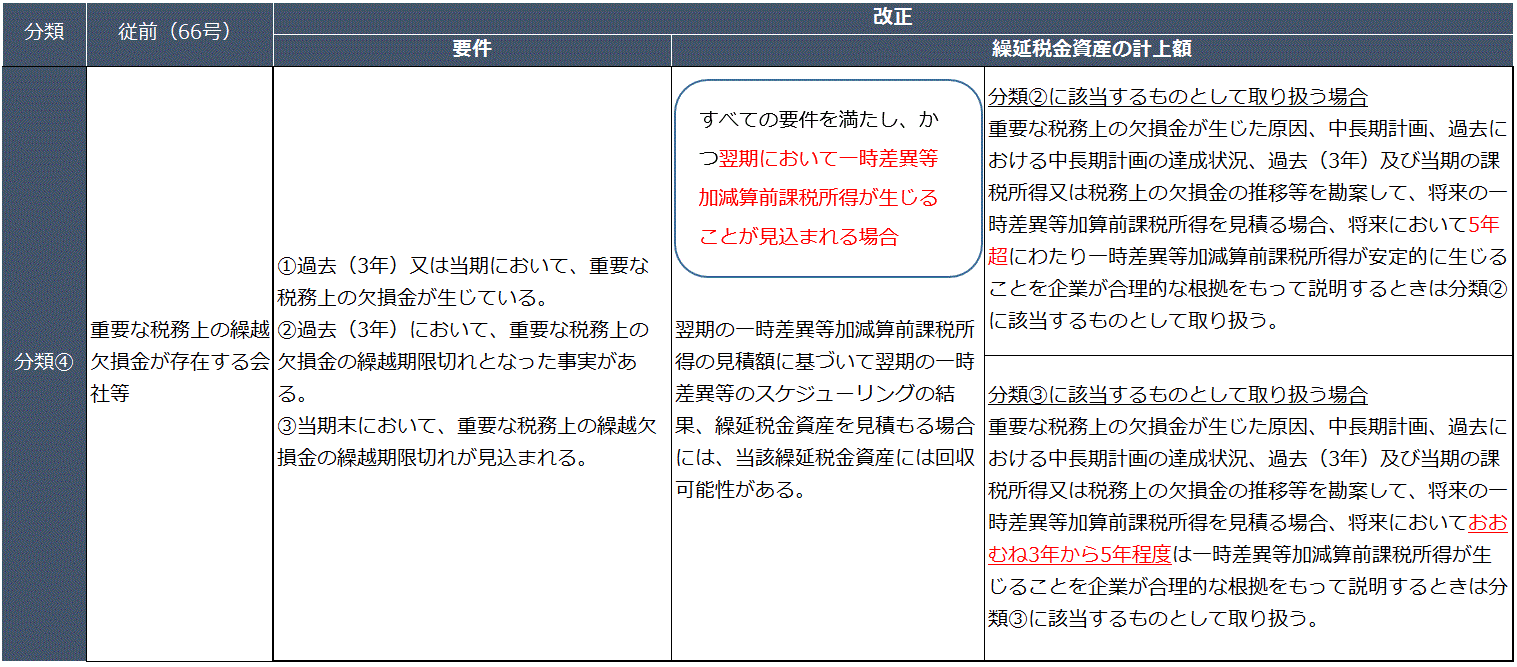
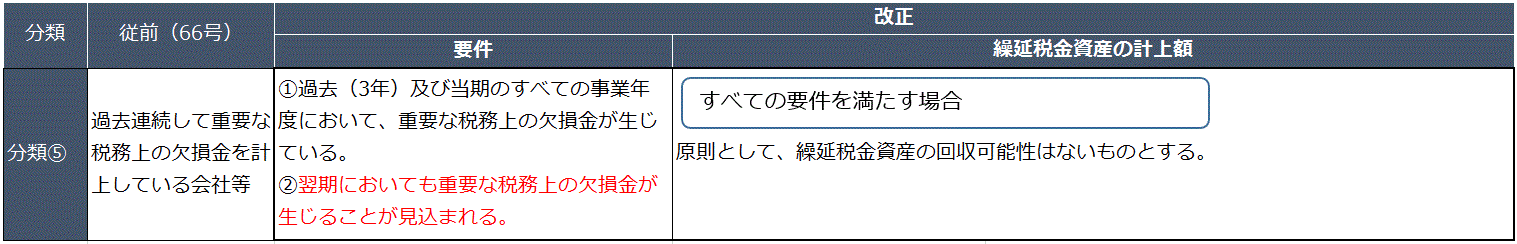
分類①~⑤にいずれにも該当しない企業の取扱い
従来は、「それぞれに例示区分に直接該当しない場合であっても、それぞれの例示区分の趣旨を斟酌し、会社の実態に応じて、それぞれの例示区分に準じた判断を行う必要がある」とされていました。
改正により、「分類①から分類⑤に係る分類の要件をいずれも満たさない企業は、過去の課税所得又は税務上の欠損金の推移、当期の課税所得又は税務上の欠損金の見込み、将来の一時差異等加減算前課税所得の見込み等を総合的に勘案し、各分類の要件からの乖離度合いが最も小さいと判断されるものに分類する」とされました。
基本的な考え方は変わりませんが、より詳細かつ具体的な取扱いとなっています。
分類②、③に係る分類の要件
従前は「経常的な利益(損益)」という会計上の利益が要件としていましたが、改正により「臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得」という課税所得が要件となりました。
会計上の利益と課税所得の金額は通常は一致しない中で、繰延税金資産の回収可能性の判断においては、課税所得の十分性を検討する必要があるため、重視すべき要件としては課税所得がより適切であるための変更です。
従前の66号では「経常的な利益」が要件となっていましたが、実務で分類判定する際には、過去の経常的な利益以外にも課税所得等の推移を加味した上で判断していることや、仮に経常的な利益を計上している会社であっても、経常利益と課税所得が近似しないような場合には、会社の実態に応じて、それぞれの例示分類に準じた判断を行っている実務があることから、この要件の変更は、個人的には本質的な変更ではないと思っています。
なお、課税所得から「臨時的な原因により生じたものを除く」とされている点に注意が必要です。過去において臨時的な原因により生じた益金及び損金は、将来において頻繁に生じることは見込まれないという推定に基づいたものになります。
ここで、
『営業損益項目に係る益金及び損金は通用の事業活動から生じたものであることから、原則として「臨時的な原因により生じたもの」に該当しないと考えられる。一方、営業外損益項目及び特別損益項目に係る益金及び損金のうち、企業が置かれた状況等に基づいて検討した場合に将来において頻繁に生じることが見込まれないものは「臨時的な原因により生じたもの」に該当することが考えられる。』
とあります。
「原則として」とあるのは、項目の性質によっては、営業損益項目であっても臨時的な原因に該当するものが含まれたり、又、特別損益項目であっても必ずしも臨時的な原因に該当しないものがあることを想定しているためです(改正適用指針71項)。
例外的な取扱いを行う場合には、その置かれた状況や項目の性質等を勘案し、個々に合理的な根拠をもって説明する必要がありそうです。
分類②におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い
従前は、分類②であればスケジューリング可能であれば繰延税金資産を全額計上することができる反面、スケジューリング不能なものは、一律に繰延税金資産を計上することができないとする取扱いでした。
改正により、スケジューリング不能な将来減算一時差異のうち、税務上の損金算入時期が個別に特定できなくても、将来のいずれかの時点で損金算入される可能性が高いと見込まれるものについては、合理的な根拠をもって説明する場合には、繰延税金資産を計上できるようになりました。
実務指針上では、政策保有株式の例示が示されていますが、これ以外にもありそうです。
たとえば、役員退職慰労引当金に係る税効果で、従前までは役員の退任時期を合理的に見積ることが困難であったことからスケジューリング不能としているケースや、逆に、いつかは退任する、ということを根拠として見積計上しているようなケースもありました。
このように、分類②のスケジューリング不能な一時差異には、正直グレーな実務が散見されていたように思いますので、例外が新たに追加されることにより(改正適用指針37項)、一定の要件を満たしたスケジューリング不能な一時差異に係る繰延税金資産は回収可能性があるものとされたことで、従前よりも白黒はっきりつけやすいのではないかと個人的には思います。
分類③における合理的な見積可能期間に関する取扱い
従前は、将来の合理的な見積可能期間(おおむね5年)内の課税所得の見積額を限度として繰延税金資産を計上できる取扱いでした。
改正により、5年を超える見積可能期間でも、合理的な根拠をもって説明する場合には、繰延税金資産を計上できるようになりました。
確かに、「5年」という表現に縛られ過ぎて、実質はほぼ5年内解消するものでも、5年を超えてる分については機械的に全額評価性引当とした経験もあるので、弾力的に運用されることには賛成です。
但し、5年先、いや3年先のことすら予想するのが難しいのに、5年を超える分について、合理的な根拠をもって説明するのは、相当ハードルが高い気がします。たとえば、ということで製品の特性により需要変動が長期にわたり予測できるものや、長期契約が新たに締結された場合が例示されていますが(改正適用指針85項)、一方で昨今の不正事例をみても分かるように、合理的な根拠をもって説明を受けた会計士としては、どのようにジャッジしていかなければならないかは、今後の大きな課題になりそうです。
分類④の企業が分類②又は③に該当する場合の取扱い
従前は、重要な税務上の繰越欠損金が存在する会社等は、翌期の課税所得の発生が確実に見込まれる場合にはその範囲内で翌期の一時差異等のスケジューリングの結果に基づいて繰延税金資産を計上できる取扱いと(本文)、重要な税務上の繰越欠損金が存在する会社等であっても、リストラを実施したなどの特別な要因に基づいて発生したものであり、それを除けば課税所得を毎期計上しているような場合は、将来の合理的な見積可能期間(概ね5年)内の課税所得を限度に繰延税金資産を計上することができる取扱いがありました(但書)。
改正により、重要な税務上の繰越欠損金が生じた原因、中長期計画、過去における中長期計画の達成状況、過去(3年)及び当期の課税所得又は税務上の欠損金の推移等を勘案して、将来の一時差異等加減算前課税所得を見積もる場合、将来において5年超にわたり一時差異等加減算前課税所得が安定的に生じることを企業が合理的な根拠をもって説明する場合には分類②、将来においておおむね3~5年程度は一時差異等加減算前課税所得が生じることを企業が合理的な根拠をもって説明する場合には分類③に該当するものとして取扱うことになりました。
要件として、当期末に重要な税務上の繰越欠損金が存在するかどうかではなく、過去(3年)又は当期において重要な税務上の欠損金が生じているかどうかに焦点があてられている点が変更されています。
また、「翌期において一時差異等加減算前課税所得が生じることが見込まれる場合」が追加されている点にも注意する必要があります。
従前の分類④但書の「非経常的な特別の原因」というものがどういう定義なのか分からず苦労させられたことや、分類③と同様に5年という表現に縛られ過ぎた経験からすると、より分類判定しやすくなっている印象です。
概要Summary
上記の概要をまとめると下記のとおりです。
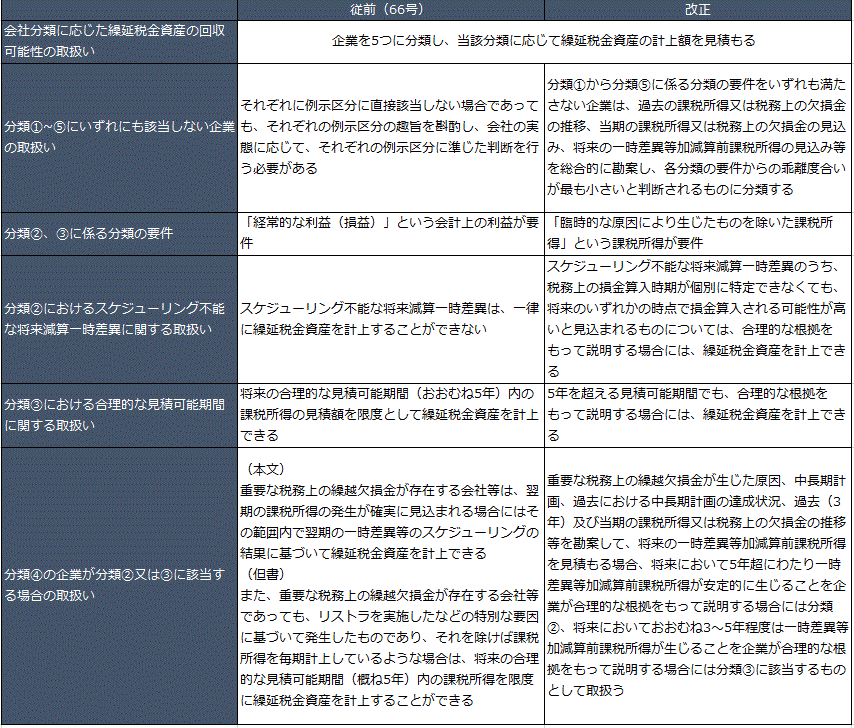
適用時期
平成28年4月1日以降開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用となります。
但し、平成28年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度の年度末から早期適用することも認められています。
3月決算の場合には、平成28年度(平成29年3月期)からの適用となりますが、事業年度の期首から適用となるので、平成28年6月の第1四半期から適用されます。
また、早期適用した場合には、平成28年3月期の四半期情報については、その期首から適用されたものとして遡及修正する必要があります。
12月決算の場合には、平成29年度(平成29年12月期)からの適用ですが、平成28年度(平成28年12月期)からの早期適用が可能です。早期適用した場合の四半期情報についても3月決算と同様になります。
改正前後で影響額が大きくなりそうな分類③や④の会社の場合には、早期適用する会社も少なくないのではないでしょうか。
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更
以下の項目を適用することにより、従来の会計処理と異なることとなる場合には会計基準等の改正に伴う会計方針の変更としての取扱いになります。
(1)分類②において、スケジューリング不能な一時差異にかかる繰延税金資産について回収できることを企業が合理的な根拠をもって説明する場合には回収可能性があるとする取扱い
(2)分類③において、おおむね5年を明らかに超える見積可能期間においてスケジューリングされた一時差異等に係る繰延税金資産が回収可能であることを企業が合理的な根拠をもって説明する場合には回収可能性があるとする取扱い
(3)分類④において、将来において5年超にわたり一時差異等加減算前課税所得が安定的に生じることを企業が合理的な根拠をもって説明する場合には分類②に該当するものとする取扱い
適用初年度の取扱い
適用初年度においては、期首時点で新たな会計方針を適用した場合の繰延税金資産(負債)と、前年度末の繰延税金資産(負債)の額との差額を、適用初年度の期首の利益剰余金に加減することになります。
但し、PLを経由しないもの(包括利益関係や評価差額金など)については、その他の包括利益累計額又は評価・換算差額等に加減することになります。
なお、過去の期間における遡及適用はなく、適用初年度の期首の影響については、繰延税金資産、利益剰余金及びその他の包括利益累計額又は評価・換算差額に対する影響額を注記することになります。
まとめ
従前の取扱いを基本的に踏襲しているとはいえ、繰延税金資産の回収可能性については、今までも多くの議論がなされており、解釈や判断の違いによって、大きく会計数値が変わってくる領域です。今般の改正でも影響を受ける会社は少なくないと思われます。
ちょうど今の時期だと、翌期以降の業績予想や事業計画等を策定している会社も多いかもしれませんが、この改正の影響を無視することはできません。
専門家や担当の監査人等と早めに協議するのが得策です。

